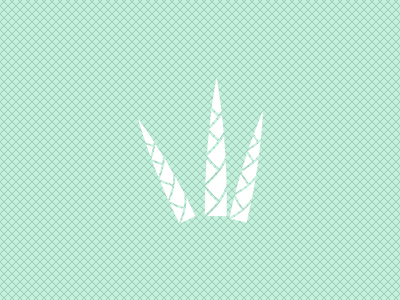神社の工事では、土台、柱の修正、壁改修以外にも石工事があります。
石工については古い神社に行けば、石畳だったり、石階段だったりと見受けられます。
そのほかにも、石燈籠だったり城壁の石垣だったりするのですが、今回については、軒先の雨落ち部にある並び石と石階段についてです。
今回の工事は、石並びを元に戻す工事になります。
石並びも月日が過ぎていく途中で、地面が動いたり土が下がったり、雨で流れたりと色々あって石の並びがまばらになってしまいます。
 ←動いたずれている石階段
←動いたずれている石階段


↑動いた雨落ちにある石(石間に大きな隙間、石が動き曲がった状態が見えます)
こういった石を敷き直します。まずは、番付を付けて、寸法と並びを調査記録してから移動し掘り起こします。角部にレベルで基準高さを出した後にを丁張をかけています。


なぜに手堀になってしまうかというと。接道が途中までしかなく、参道で丘の上にあるため、機械の搬入が出来ないなのでこういった人力になってきています。

んで、石の下を掘り起こした後の写真ですが、思ったより深く掘ってあります。これは石の下に砕石とベースを設置しその上に石を据えることで一体になって動くのを防ぐようになります。

石段周りに、”たち”を修正し、(石が重たいので、ジャッキを使って仮に支持固定している)次の工程に移ります。

今回は、ここまでで次回に期待。